(この記事は2025年6月16日に更新されています)
アフリエイト広告を利用しています。

指示待ち・応用が利かないと評価が下がる?
介護現場で「仕事ができない」と評価されてしまう背景には、いくつかの共通点が見られます。
特に大きな要因として挙げられるのは、「指示がないと動けない」「イレギュラーな事態に対応できない」といった傾向です。
仕事に慣れてくると、指示がなくても「次に何をすべきか」を自ら判断し、行動できるようになるのが理想です。
しかし、自分の役割や業務の全体像を理解できていない場合、上司からの指示に対しても期待通りの成果を出せないことがあります。
これは、自身のポジションや業務における役割を十分に把握できていないことに起因します。結果として、上司が求めるレベルの仕事ができなかったり、頑張っていても評価に繋がらなかったりする状況が生まれてしまいます。
ルールが増えるのは「仕事の質」が低下しているサイン?
介護施設では、不定期に新しいルールが設けられることがあります。これは、大きく分けて2つのケースが考えられます。
- 新しい業務やサービス開始に伴うルールの新設: これは職員全員に周知徹底が必要なため、当然のことと言えます。
- 既存業務の質のばらつきや問題発生によるルールの追加・見直し: 例えば、職員間で業務の進め方に統一性がなく、サービスの質に問題が生じている場合や、個々の判断でスピードを重視しすぎた結果、ご利用者様への不快感や事故のリスクが高まっている場合などです。
後者のケースは、職員の仕事の質が低下している、あるいは効率性ばかりを追求して個々が独自のやり方をしていることが原因で発生します。
本来、ルールがなくても現場の情報共有や共通認識によって、一定の仕事の意識や技術レベルが保たれるのが望ましい姿です。
しかし、それができていないからこそ、やむを得ずルールという形で業務の基準が定められてしまうのです。
これは、弁護士の水野祐氏が朝日新聞の記事(2024年12月3日付)で「思考停止せずに見直そう」と提唱された内容にも通じます。
水野氏は、企画展「ルール展」の事例を挙げ、当初は制限を設けなかったものの、
来場者の行動によって「写真撮影の可否」や「静かにする」といった制限的なルールが増えていったと指摘しています。
このように、本来は相互作用によって成り立たせたいものが、うまくいかない場合にルールが増えていく状況は、介護現場に限らず多くの職場で起こり得ることでしょう。

「ルールだから」で思考停止していませんか?
ルールが増える環境は、職員一人ひとりの「ルールへのリテラシー」が低いことを示唆している可能性があります。
水野氏も指摘するように、ルールを単に「守るもの」と捉え、思考停止してしまうと、結果的に自由な発想や応用力が失われてしまいます。
介護の仕事は、ご利用者様一人ひとりの状態や状況が常に変化するため、イレギュラーな事態への対応が不可欠です。
「ルールだから」という理由だけで目の前の業務をこなしていると、普段と異なる状況に直面した際に適切な判断ができず、「仕事ができない」と評価されてしまうリスクが高まります。

「仕事ができる」と評価される介護職になるためには?
では、「仕事ができる」と評価されるようになるためには、どうすれば良いのでしょうか。
重要なのは、目の前の業務やルールに対して「なぜ?」という問いを常に持ち、その根拠を深く理解することです。
1. 業務の「なぜ」を深掘りする
例えば、「なぜこの時間に水分補給を行うのか」「なぜこのような介助方法が推奨されているのか」といったように、日々の業務一つひとつに対して「なぜ」を問いかけ、その背景にある根拠を理解するよう努めましょう。
ご利用者様の安全確保、身体機能の維持、QOL(生活の質)向上など、必ず何らかの理由があります。この根拠を理解することで、単に手順を覚えるだけでなく、状況に応じた判断力や応用力が養われます。
2. ルールを「使う」意識を持つ
ルールは、私たちの仕事や生活をより良く、安全にするための「道具」です。単に「守るもの」として従うだけでなく、「どうすればこのルールを活かして、より良いケアを提供できるか」「このルールは今の状況に合っているのか」といった視点で捉えてみましょう。
もし、現在のルールが現場の実情に合わないと感じる場合は、その根拠を明確にした上で、改善提案を行うことも重要です。主体的にルール形成に関わる意識を持つことで、自分たちの仕事がより円滑に進むようになります。
3. 根拠を意識した情報共有と実践
業務の根拠を理解したら、それを同僚と共有し、互いに学び合う姿勢も大切です。疑問に思ったことは積極的に質問し、自分で調べたり、経験豊富な先輩にアドバイスを求めたりすることで、知識と経験が深まります。
最初は時間がかかると感じるかもしれませんが、この「なぜ」を追求し、根拠を理解するプロセスを繰り返すことで、自然と仕事のスピードと質が向上していきます。ご利用者様に対しても、根拠に基づいたケアを提供できるようになるため、安心感を与えることにも繋がります。
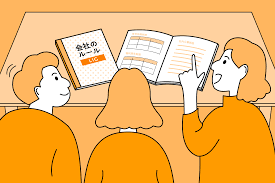
自律的な学びがプロフェッショナルを育む
業務の根拠を理解し、それを共有するプロセスは、単に個人のスキルアップに留まりません。
チーム全体の知識レベルを引き上げ、より質の高い介護サービスを提供するための基盤となります。
介護現場は日々変化し、ご利用者様の状態も常に移り変わります。そうした中で、マニュアル通りではないイレギュラーな状況に直面することは少なくありません。
しかし、業務の根拠を深く理解している介護職は、たとえ前例のない事態に遭遇しても、冷静に状況を分析し、適切な判断を下すことができます。
なぜなら、目の前の事象がなぜ起こっているのか、どのようなリスクがあるのか、そして、どのような対応がご利用者様にとって最適なのかを、根拠に基づいて論理的に考えられるからです。
この「考える力」こそが、介護職としての専門性を高め、プロフェッショナルとしての自信へと繋がります。
また、自ら「なぜ」を追求し、解決策を探す姿勢は、介護職自身のモチベーション維持にも大きく貢献します。
指示されたことをこなすだけの受け身の働き方では、仕事へのやりがいを感じにくくなることがあります。
しかし、自分の頭で考え、行動し、それがご利用者様の笑顔や安心に繋がった時、介護職は大きな達成感を得られるでしょう。
さらに、根拠に基づいたケアは、ご利用者様やそのご家族との信頼関係を深める上でも不可欠です。
なぜこのケアが必要なのか、どのような効果が期待できるのかを、明確な根拠とともに説明することで、安心感を与え、納得してサービスを受けていただけます。
これは、介護職の信頼性を高め、質の高いコミュニケーションを築く上で非常に重要な要素です。
介護の仕事は、まさに「学び続ける」ことが求められる仕事です。
日々の業務を通じて新たな知識を獲得し、疑問を解消し、それを実践に活かすことで、
自身の成長を実感できるでしょう。そして、その成長が、結果としてご利用者様へのより良いケア、ひいては介護業界全体の発展へと繋がっていくのです。
まとめ:介護の仕事は「人間力」を磨く場
介護の仕事は、単に身体介護を行うだけでなく、ご利用者様の生活全体を支え、その人らしい人生を送れるようにサポートする、非常に専門性が高く、かつ人間力が求められる仕事です。
「仕事ができない」と評価されてしまう現状を打破するためには、指示待ちの姿勢から脱却し、自ら考え、行動する主体性が不可欠です。
そして、その行動の裏付けとなる「なぜ?」を深掘りし、根拠を理解する思考力を養うことが重要です。
このプロセスは、介護のスキルアップだけでなく、人生におけるあらゆる場面で役立つ「考える力」を育みます。自分自身を成長させながら社会に貢献できる介護の仕事は、大きなやりがいを感じられる素晴らしいキャリアパスです。
もし、あなたがキャリアアップを考えていたり、新たな挑戦を求めているのであれば、ぜひ一度、介護業界での可能性を検討してみてはいかがでしょうか。
【介護職の転職を応援!】
経験豊富なキャリアアドバイザーがあなたにぴったりの職場を見つけるお手伝いをします。
介護職専門の転職サイト【ケアジョブ】で、あなたの新しい一歩をサポートします!


最新の医療の紹介として・・・
幹細胞クリニック東京のご紹介
幹細胞クリニック東京は再生医療に特化したクリニックです。国内製造で厳しい基準を満たした安全性の高い幹細胞培養上清液(エクソソーム)治療を提供し、経験豊富な医師が患者様一人ひとりに最適な治療をご提案いたします。また、わかりやすい料金プランや完全予約制により、安心して治療を受けていただける環境を整えております。」
【https://kansaibou-clinic.or.jp/】




コメント