アフィリエイト広告を利用しています。

介護職で「自分だけ仕事が多い」と感じたら? – 辞めるべきか、続けるべきか
介護の仕事を選んだ理由が「とりあえず」だったとしても、誰もが働き始めてから「この仕事、なんか違うな」「自分だけ忙しすぎる」と感じることがあるかもしれません。特に、同じ条件で採用された他の職員と比べて、自分だけが過剰に業務を抱えているように感じると、「このまま仕事を続けるべきか?」と悩んでしまいますよね。
このブログでは、介護職でそうした悩みを抱えるあなたへ、その理由と、今後どう行動すべきかについてお伝えします。
なぜ「自分だけ仕事が多い」と感じてしまうのか?
介護の仕事は、単なるルーティン作業ではありません。利用者さん一人ひとりの状況に合わせたオーダーメイドの支援が求められます。そのため、効率だけを追求する働き方では、利用者さんの本当に必要なケアを見逃してしまうこともあります。
もしあなたが「自分だけ仕事が多い」と感じているなら、その背景にはいくつかの理由が考えられます。
- 仕事への価値観の違い: あなたが利用者さん一人ひとりに深く寄り添い、丁寧なケアを心がけている一方で、他の職員は時間内に業務を終わらせることを最優先しているのかもしれません。
- 「とりあえず」で始めた仕事への向き合い方: 介護職を「生活のため」や「早く働ける場所」という理由で選んだ場合、仕事への熱意やコミットメントが、他の職員と異なる場合があります。これが、仕事への取り組み方や、結果的な業務量の違いに繋がっている可能性があります。
- 業務の質と深さの違い: あなたは、目に見えにくい利用者さんのニーズや課題を発見し、それに対応するケアに時間を費やしているかもしれません。これは非常に重要な業務ですが、外からは「作業量」として見えにくいこともあります。
「仕事が多い」と感じた時、辞めるべき?続けるべき?
同じ条件で採用された同僚と比べて業務量に偏りを感じた時、すぐに辞めるべきかどうかは慎重に考える必要があります。
辞めることを検討しても良いケース
- 心身の不調: 仕事の負担が大きすぎて、精神的または肉体的に疲弊しているなら、立ち止まって健康を最優先に考えるべきです。
- 仕事内容への不満と改善の見込み: 自分の理想とするケアと現実の業務内容がかけ離れており、今後も改善される見込みがないと感じるなら、他の選択肢を探すのも一つです。
- 不当な評価や報酬: 仕事量が多いにも関わらず、それが正当に評価されず、給与にも反映されていないと感じるなら、モチベーションを維持するのが難しくなるでしょう。
- 他の仕事への強い魅力: 介護職以外の仕事に、もっと大きなやりがいや成長の機会を感じるのなら、検討してみる価値はあります。
辞める前に試してほしいこと
- 現状の可視化と整理: どのような業務にどれくらいの時間を費やしているのか、具体的に書き出してみましょう。これによって、業務量の偏りがより明確になるかもしれません。
- 上司や同僚への相談: 「なぜ自分だけ仕事が多いと感じるのか」という疑問を、具体的な事例を挙げながら、上司や信頼できる同僚に相談してみてください。業務分担の見直しや、効率化のためのアドバイスが得られる可能性があります。
- 自身の業務効率の見直し: あなた自身の動きに無駄がないか、効率化できる部分はないか、改めて考えてみることも大切です。プロとして、効率的な働き方を追求する視点も重要です。
- 介護の仕事の「やりがい」を再確認: もしあなたが、利用者さんとの関わりの中に喜びや自身の成長を感じているのであれば、一時的な業務量の不公平感に捉われず、この仕事ならではの価値に目を向けてみましょう。介護の仕事は、利用者さんの人権、尊厳、自己決定、自立支援を根底に、人としての成長を促す多くの学びがあります。
まとめ
介護の仕事は、単なる作業の繰り返しではありません。それは、利用者さんの人生と深く関わり、人としての尊厳を支える、奥深くやりがいのある仕事です。
もしあなたが、介護職にそうした価値を見出し、自身の成長に繋がると感じているなら、安易に辞めるのではなく、まずは現状改善のためにできることを試してみてはいかがでしょうか。一方で、心身の健康を損なうほど負担を感じているのであれば、ご自身の心と体の健康を最優先に考え、新たな道を検討することも決して間違いではありません。
あなたの価値観と、目の前の仕事、そして未来のキャリアについて、じっくりと向き合ってみる良い機会になることを願っています。
ここからは、わたしの職場を通じての感想を書いています。
じつは、私の勤める介護施設でも、辞めていく人の中には、違う介護施設に転職を決める方と、
介護のお仕事から撤退したい方がおられます。
介護の仕事はもうしない、その理由は、やはり、作業として、時間内に終わらせることだけが、目的だったように感じました。
そして、違う仕事を探すとのことでした。
もともとの本当の入職動機が大きく影響しています。

しかし、例外もあると思います。
私のように、取り敢えず、介護施設への転職を決めて未経験からのスタートでも、
介護のお仕事の学びの多さに魅力を感じて、続けられる方もいます。
そうすると、どんな仕事で働くにしても何か自分自身でやりがいや面白さを見つけたもの勝ちのようです。
自分の仕事を介護のお仕事で頑張ると決めた時に、取り敢えず、生活費が入れば良い、
就職活動もしくは、転職活動で、早く働ける場所を決めたいという理由で、
取り敢えず、介護のお仕事を選ぶと、どうしても、心身ともに疲れてしまい、
長く続けることが、難しいお仕事のようです。

介護のお仕事で一緒に働く職員さんにも、どうしたら、早く仕事が終えられるか、
どうしたら、無駄な時間を使わず、できるだけ楽に効率的に動けるか、
できるだけやるべきことを最優先して、体力を温存するかを考えている職員さんも見かけます。
無駄な動きを無くす、効率的に動く、という考え方はとても優秀な方だと思います。
何か、イレギュラーな事が起きたときに対応できるように、時間を作るようにして業務を進めることは、
大変、仕事のプロとしては、大切なことで、私自身も学ばなければならいことが多いと感じています。
仕事に限らず、あらゆることは優先順位を考える上で、段取りよく、効率よく仕事をすることは、大切です。
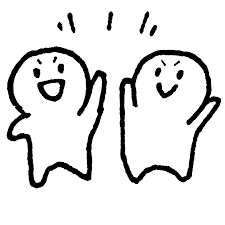
しかし、理想と現実は違います。
介護のお仕事では、利用者さんが中心でなければならないことを考えると、介護職の思うままに業務が進行しない日があっても仕方ないことも出てきます。
たしかに、仕事の後に、ご家庭の用事やプライベートの予定も非常に大切ですので、
時間通り仕事を進めていきたいものです。
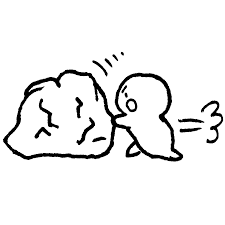
しかし、どうしても自分の予定が少し遅れそうになったり、もしかしたら中止しなければならない、変更しなければならない時も出てくることもあり得ます。
そんなときでも、介護のお仕事を嫌な仕事と感じない人とはどのような人でしょうか。
おそらく、介護の仕事が好きで介護業界に就職された方でしたら、
急な残業が起きても、仕事が辛くて、辞めたいとまでは、行かないかも知れません。
介護施設が利用者さんにとっては、終の棲家という方もおられると思います。
もしかしたら、何かの事情で、他に帰るところがないという方も多いと思います。

介護施設が自宅として生活をされている方にとって、もし介護職員が単に生活費を稼ぐために仕方なく仕事をしていて、
早く帰宅したいために、時間短縮の効率最優先な介護の仕事をしていたら、
利用者さんのことを見ること(観察すること)ができなかったり、
その利用者さんのニーズや課題を発見する機会を逃してしまうこともあります。
介護職員の慌てる行動で、不適切なケアに繋がり、やがて虐待行為として、捉えられる可能性も出てくるこことがあれば、大きな問題になってしまいます。

費用対効果の考えは前職の営業の時には、毎日、上司から強烈に意識するように指導されていました。
営業の仕事では、数字を上げないことには、仕方がなく、
とにかく、経費削減と見込み顧客の取りこぼしがないようにするためには、その意識はとても大切なことです。
しかし、介護施設へ転職して思うことは、営業の仕事でも、
やはりお客様を見ることができなければ、営業の成果は出にくいということです。
お客様を大切に考えることは、介護施設でも、ご利用者様を大切にすることは、ともに、自分中心ではない考え方になります。

お客様に必要な時に必要なものを納得していただける価格で購入していただき、また、その良かった営業マンを紹介したいと、新たに、お客様をご紹介していただけることにも繋がります。
結局、どのような仕事に就いても自分中心では、うまくいかないということが、職種を変えてみて、ようやく気付いた次第です。
介護の業界でも、いろんな研修があります。
そして、基本となることは、やはり、利用者さんの人権、尊厳、自己決定、自立支援、についてが根底にあります。
このことは、私たちが生きてゆく、あらゆる生活の場面でも、求められることです。
このようなことは、義務教育で学んだときがあったとしても、
すっかり記憶から薄くなっていると思います。
ですので、社会人になってから、改めて仕事や人生という実践の中で、
学び直すことは、人生を豊かになれることだと思います。

人権、尊厳、自己決定、自立支援、について、これらが、生きていく上で、
すべてに共通する人生の大切なキーワードであることを、ご理解をいただけるのは、
きっとある程度、社会経験をされた方になるかも知れません。
仕事を通じて、人生を豊かに、そして、自分自身が成長できるお仕事として、介護のお仕事で幸せになる方が増えることを願います!





コメント